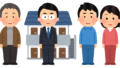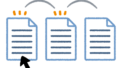源泉徴収される士業
今まさに法定調書合計表の作成の真っ最中です。
合計表の作業をしていると、毎年のように疑問に思うのは、 「なぜ行政書士の報酬には源泉所得税がかからないのか」という点です。
行政書士の報酬については源泉所得税がかからないため、 支払調書の提出も不要とされています。
そもそも支払調書というものは、「源泉徴収の裏付け資料」としての性格を持つ書類だからです。
(支払調書の提出も不要というのは、意外と見落とされがちなポイントかもしれません)
例えば、税理士に支払う報酬については、 顧問先が源泉所得税を控除し、その源泉所得税を税務署に納付します。
そして、源泉所得税の対象となるのは、税理士の報酬だけではありません。
以下の士業の報酬も、源泉所得税の対象となります。
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 公認会計士
- 社会保険労務士
- 弁理士 等
これらは所得税法204条に規定されています。
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
この条文の中に、「行政書士」という文字は出てきません。
なぜ所得税法204条に列挙されていないのか
調べてみると、さまざまな臆測や解説が見つかりますが、 なぜ所得税法204条に行政書士が列挙されていないのかについて、 はっきりとした理由は確認できませんでした。
行政書士会や国税庁による、 公式な見解も示されていないのが実情です。
各種AIにも質問してみましたが、 個人的に最もしっくりきたのは「Claude」の次のような回答でした。
報酬水準 – 制度設計当時、他の士業と比較して報酬水準が比較的低く、徴税効率の観点から優先度が低かった可能性
立法時の政策判断 – 所得税法204条で対象士業を列挙する際の、何らかの政策的・行政的判断
行政書士は他の士業に比べて報酬水準が低かったためなのか
(もっとも、現在では高い報酬を得ている行政書士の先生もいらっしゃいますが)、
それとも立法時における政治的・政策的判断だったのか。
もしそうであれば、時代の変化に合わせて「改正すべきでは」とも考えられますが、
なぜ今日までそのまま維持されてきたのかは、よく分かりません。
行政書士だけが例外というわけではない
報酬が源泉徴収されないのは、行政書士だけではありません。
所得税法204条には、次の資格も列挙されていません。
- 中小企業診断士
- 宅地建物取引士
中小企業診断士については、
- 国家資格ではあるものの、独占業務がない
- 企業内診断士が多く、独立開業者ばかりではない
- 現在の制度は2000年に確立された比較的新しい資格
といった点から、源泉徴収の対象とされていない、 という説明は比較的納得しやすいように思います。
宅地建物取引士も、 資格単体で独立開業する性質のものではないため、 報酬は源泉所得税の対象にはなりません。
それでも源泉徴収が必要になるケースがある
行政書士の報酬であっても、 例外的に源泉徴収が必要となる場合があります。
つまり、その場合には支払調書の提出が必要となります。
国税庁のサイトには次のような記載があります。
しかし、例えば、依頼した業務が建築基準法第6条等に定める「建築に関する申請若しくは届出」の書類の作成のような場合には、その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、支払調書の提出が必要になります。
これを見ると、 行政書士がよく行う「建設業許可申請」と混同される方もいるかもしれませんが、
- 建設業許可申請
- 建築代理士の行う業務
は、まったく別の業務です。
<建設業許可申請→源泉徴収が不要=支払調書の提出が不要>
建設業を営むための、
- 許可申請
- 更新
- 業種追加
- 経営事項審査 など
<建築士の業務領域→源泉徴収が必要=支払調書の提出が必要>
建物の、
- 建築確認申請
- 建築計画変更届
- 完了検査申請 など
もっとも、 行政書士報酬として建築士の業務領域に該当するものを 実務で目にする機会は、それほど多くはないのが実情でしょう。
まとめ
行政書士の報酬に源泉所得税がかからない理由は、 制度としては明確でも、 その背景までは必ずしも明らかにされていません。
とはいえ、「そういうルールだ」と押さえておけば、実務で迷うことはほとんどありません。
法定調書合計表を作成する際の、 ちょっとした整理材料として、 本記事が参考になれば幸いです。